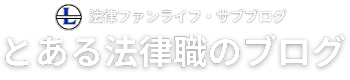独学でブログ運営をやっていると、記事タイトルについては何か共通する要素(オーソドックスな方法論)はあるらしいものの、他にも調べることが多くあったりして、案外、具体的な方法論を知らずに来てしまうこともあります(管理人自身の話)。
オーソドックスな方法論に合わせるかどうかは別として、知っておくことは大事だろうと思いますし、自分の好みと合う範囲で取り入れることもできるはずです。
また、「記事タイトルが短かすぎるとSEO的には不利」という一般論を見かけることがありますが、個人的には「ほんとにそんなに影響してるのか??」という体感値があり、気になっていました。
そこで、本記事では、記事タイトルのつけ方(特に長短)を取り上げ、
記事タイトルをつけるに当たって押さえておくべき考え方は何か?
という悩みどころと、現時点でのひとつの考え方をFAQ形式でまとめてみます。
記事タイトルの付け方(特に長短)
タイトルの付け方に関して、「タイトルが短かすぎるとSEO的に不利」という一般論がある。ただ、体感値としては、長かろうが短かろうが、あまり関係なく上位になっていたり下位になっていたりするので、あまり関係がないようにも感じる。この”タイトルの長さ”というのは、実際のところどのくらいSEOに影響するものなのか。
SEOにおけるタイトルの長さについては、確かに「短すぎると不利」といった一般論があるが、実際には直接的な順位要因ではなく、間接的に影響する要素として理解するのが現実的である。
タイトルの長さは「直接的なSEO要因」ではない
Googleのアルゴリズムは、タイトルの長さそのものを評価して順位を決めているわけではない。つまり、
- 「タイトルが短いから順位が落ちる」ことはない
- 「タイトルが長いから上位表示される」こともない
というのが基本となる。
では、なぜ「タイトルは長いほうがいい」と一般に言われるのかというと、タイトルが検索意図に合致するキーワードを網羅していると、クリック率や関連性が高くなりやすいからである。
つまり、長さというより
- 主キーワードと副次キーワードが自然に含まれているか
- 検索ユーザーが求めている内容を想起させるか
- CTR(クリック率)が上がるような魅力ある表現か
という点が重要であり、それらは結果として長いタイトルになることがあるというだけ。
そのため、体感値として感じている「タイトルの長さはあまり関係ない」というのも別に間違っておらず、タイトルの長さを変えても順位に変化がなかったのであれば、それは他の要因(記事内容、検索意図との一致度、外部リンクなど)のほうが圧倒的に支配的であることを意味する。
実際に気にすべきは「検索意図への合致」と「見やすさ」
実際に気にすべきはあくまでもタイトルの内容であり、
- 検索ユーザーが入力しそうな語句(主キー、副キー)が自然に入っているか?
- タイトルが長すぎて途中で切れて、意図が伝わらなくなっていないか?
⇨目安はPCで約30字、モバイルで約40字まで(あくまで表示上の目安) - タイトルが何についての記事かを一瞬で伝えられているか?
といったことがポイントとなる。
こうしたポイントをおさえていれば、「20字」でも「40字」でも、SEO上は何ら問題はない。
主キーと副キー
「主キーワード」と「副次キーワード」とは何か。
SEOにおける「主キーワード」と「副次キーワード」は、検索意図を捉えるうえで重要な概念である。それぞれの役割や違いを整理しておくとよい。
主キーワードと副次キーワード
主キーワード(メインキーワード)とは、記事の主題そのものを表すキーワードであり、ユーザーが検索する際の「もっとも基本的で核心的な語句」を指す。
使い方としては、①タイトルやh1見出しに必ず入れるようにするとともに、②URLスラッグ、メタディスクリプション、本文の冒頭(リード文)にも自然に含めるのが望ましい。
主キーワードと副次キーワードの違いをまとめると、以下のようになる。
| 要素 | 主キーワード(メイン) | 副次キーワード(サブ) |
|---|---|---|
| 意味 | 記事全体のテーマ・中心語 | テーマの具体化・補足語 |
| 重要度 | 最重要、必ず含める | あると便利、複数含める |
| 役割 | 記事の主軸をGoogleと読者に伝える | ユーザーの詳細なニーズに応える |
| タイトルでの位置 | 前半が望ましい | 無理なく自然に入れる |
具体例
例えば、契約の解除条項について記事にする場合、
「契約書の解除条項とは?通知・理由・違約金の扱いをわかりやすく解説」
などというタイトルが考えられる。これは、
- 主キーワード:「契約書 解除」が前半にあり
- 副次キーワード:「通知」「理由」「違約金」も含まれている
といえる。
他にも、ジャンル別に整理すると、たとえば以下のようなイメージが考えられる。
| ジャンル | 主キーワード | よくある副次キーワード例 |
|---|---|---|
| 契約法務 | 契約書 解除 | 違約金、通知、条文、協議、解除条件 |
| 労務管理 | 残業代 | 計算方法、未払い、請求、時効 |
| 情報管理 | 個人情報 | 第三者提供、委託、保管、同意書 |
| コーポレート | 株主総会 | 議事録、決議要件、オンライン開催 |
補足:見出し(h2, h3)にも副キーを活かす
また、見出し(h2, h3)に副次キーワードを盛り込みながら、検索者が求める具体情報に到達できるような記事構成にすると、SEO効果がより高まる。
本当にそうか?(埋没しないか?)
現実にこのようなタイトルで記事にしていった場合、だいたい同じようなタイトルになっていくので、却って埋没するというようなことはないか。
たしかに、SEOと実際の検索行動・クリック行動には、論理的な最適解と、心理的・感覚的な実態とのあいだにズレが生じることがある。まさにその“ズレ”をうまく突いたのが、「短いけど気になるタイトル」や「敢えて曖昧にしたタイトル」が意外と強い、という現象である。なぜそれが起きるのか・どのようにバランスをとるべきかを整理しておくとよい。
現実の検索行動では「目立つ」「気になる」=クリックされる
Googleは確かに「検索意図に合致するコンテンツ」を評価するが、そのための指標のひとつが「CTR(クリック率)」である。
つまり、
- タイトルが多少短くても、他と違って「目に止まる」ものはクリックされやすい
- クリックされれば、Googleは「ユーザーに刺さっている」と判断し、順位を上げる可能性がある
といえる。
長いタイトル・短いタイトルそれぞれの功罪
典型的な長文タイトルは、正確で親切であるが、デメリットとして、
- 競合記事とフォーマット・語句が被りやすく「埋没」しやすい
- 視認性が低く、スマホでは途中で切れる
- 知識がありそうな読者ほど「読むまでもない」と感じてしまう
といった問題もある。
そのため、ユーザー心理を突く「短いタイトル」が逆に目を引く場合がある。これらは主キーが完全には入っていないため検索順位には不利に働く可能性があるものの、
- 強い“気になる感”を与える
- 他のタイトルとの違いが視覚的にも明確
- SNSやニュース的な流入で高いCTRを生む可能性がある
という面もあり、こうしたタイトルは逆に目立つという点において、有効な差別化戦略にもなり得る。
実験的にA/Bテストをやってみるという選択肢もアリで、たとえば、ブログでは、
- 記事URLは変えずに、タイトルだけ数週間ごとに差し替えてみる
- アクセス数やクリック率の違いを見て傾向をつかむ
といった方法も有効である。
結び
今回は、ブログ運営記ということで、記事タイトルのつけ方(特に長短)について書いてみました。
長すぎてもわかりくい・検索結果で省略されるという面と、一方で、 短すぎると魅力が伝わらない・必要な情報も伝わらないという面があり、そのバランスをとるのがポイントです。
また、単にタイトルの長短だけ考えるより、主キーと副キーといった概念を頭に入れて考えれば、よりベターなタイトルを考える取っ掛かりになると思います。
個人的にはあまり長いタイトルや、だいたい同じものに収斂していくタイトルは好みではないのですが、出来る範囲でこのような考え方を踏まえつつ、タイトルを付けていこうかなと思います。
以上、ブログ裏話でした。