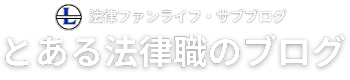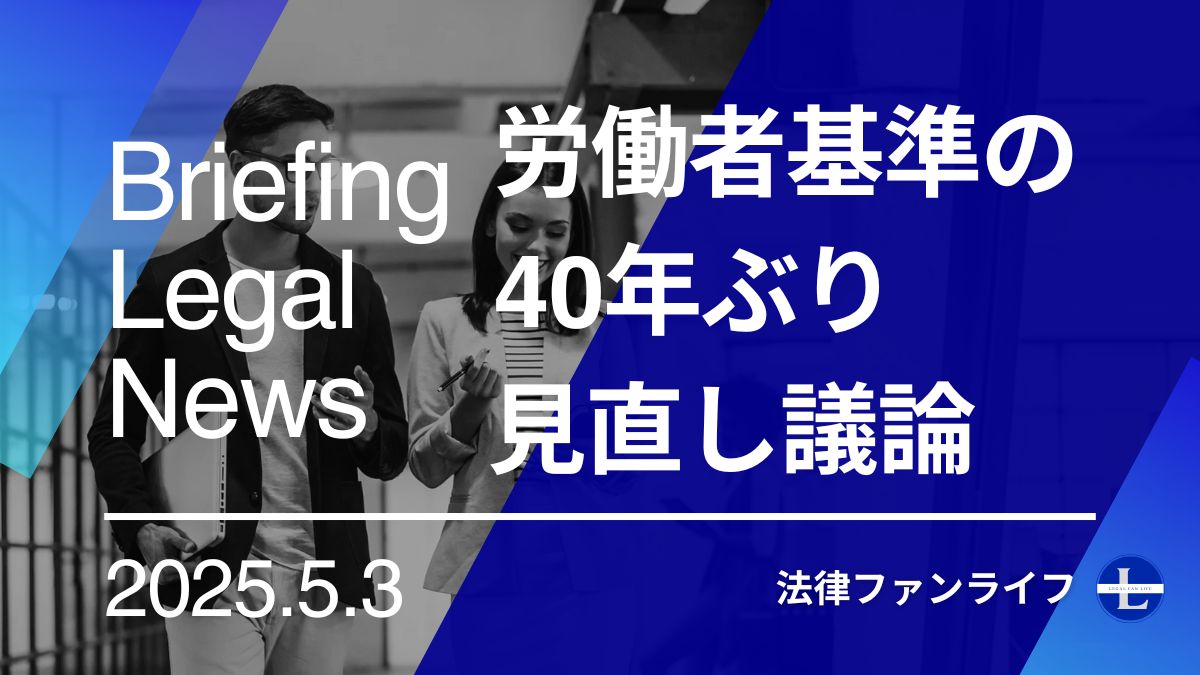本日、労働基準法上の「労働者」にあたるかどうかの判断基準を厚生労働省が40年ぶりに見直す、というニュースがありました。
これは、けっこう大事な転換点になる可能性があるかなと思うので、ざっと見てみます。
この記事はnoteにもサマリー版を掲載しています
本日のピックアップニュース
-「労働者」基準、40年ぶり見直し ギグワーカー増で厚労省が研究会 賃金や健康、保護手厚く|日本経済新聞-
-
-
「労働者」基準、40年ぶり見直し ギグワーカー増で厚労省が研究会 賃金や健康、保護手厚く - 日本経済新聞
厚生労働省は労働基準法上の「労働者」にあたるか判断する基準を40年ぶりに見直す。個人事業主として宅配などを請け負うギグワ ...
www.nikkei.com
内容はまだわかりませんが、労働基準法をはじめとした労働関連法制の適用の有無が決まってくるので、けっこう大きな変化になるかもしれないなと思います。
あらたな研究会の設置
令和7年5月2日に、厚生労働省がこの問題に関する研究会を発足させたとのことです。
「労働基準法における『労働者』に関する研究会」という名称です。
現在の判断基準
ちなみに、これまで長く通用している「労働者」基準は、昭和60年に当時の労働基準法研究会が出した報告によるものです(昭和60年労働基準法研究会報告)。
具体的には、
労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」(昭和60年12月19日)
というものです。
以下の厚労省ページで、詳しく解説されています。
なぜ「労働者」が大事なポイントになってくるかというと、民法は役務提供関係を
A:雇用
B:請負
C:委任
の3タイプに分けて規定していますが、A(労働者つまり使用従属性のあるもの=従業員タイプ)だと労働基準法その他の労働保護法制の適用を受けるのに対して、B・C(業務委託つまりアウトソーシング=外注タイプ)だと受けないことになるので、その区別がかなり大きな違いになってくるということです。
そして、かいつまんでいうと、昭和60年報告は、「使用従属性」の判断要素として
◇指揮監督下の労働
① 仕事の依頼、業務の指示等に対する諾否の自由の有無
② 業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無
③ 勤務場所・時間についての指定・管理の有無
④ 労務提供の代替可能性の有無
◇報酬の労務対償性
⑤ 報酬の労働対償性
◇限界的事例で労働者性の判断を補強する要素
⑥ 事業者性の有無(機械や器具の負担関係、報酬の額など)
⑦ 専属性の程度
⑧ 公租公課の負担(源泉徴収や社会保険料の控除の有無) 等
を挙げており、これらの総合判断で労働基準法の「労働者」該当性が判断される、ということになっています。
結局、昨今のギグワーカー等の法的な位置づけについても、実態が雇用に近いのに形式が外注ということで、偽装請負etcと根っこというか構造は同じ問題だといえます。
現在のところ、あくまでも外注であるという形式に基づいてビジネスモデルや体制をつくっている業態や会社はそこそこあると思いますので、それなりに影響が出る可能性もあるのかなと思います。
結び
以上、サクッと法律ニュースでした。
偽装請負etcについての詳しい解説はメインブログにまとめていますので、リンクからぜひご覧ください🔗
-

-
間接雇用等の類型|労働者供給・派遣・請負・出向の違い
今回は、間接雇用等の類型ということで、労働者供給・労働者派遣・請負・出向の違いについて見てみたいと思います。 偽装請負と ...
houritsushoku.com
[注記]
本記事は管理人の私見であり、管理人の所属するいかなる団体の意見でもありません。また、正確な内容になるよう努めておりますが、誤った情報や最新でない情報になることがあります。具体的な問題については、適宜お近くの弁護士等にご相談等をご検討ください。本記事の内容によって生じたいかなる損害等についても一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。