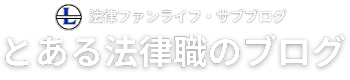本記事では、SNS上で他者の投稿をリポスト(リツイート/シェア/引用リツイート等)する行為について、想定される主要な法的リスクを整理してみたいと思います。
結論を先にいうと、単純なワンクリックの拡散行為であっても、著作権・人格権/名誉毀損/プライバシー/個人情報/営業秘密など、複数分野で責任が生じ得ます。
アミューズの法務部がおもしろいポストを出していましたので、ここを取っ掛かりにして見ていきます。
本日のピックアップPOST
いつもアミューズ所属アーティストをご愛顧くださり、ありがとうございます。
— 株式会社アミューズ 法務部 (@AmuseLegal) November 8, 2024
アーティストの活動に関する応援・感想等の投稿も大変励みになっています。
そのような温かい投稿に加え、著作権、パブリシティ権等の権利侵害行為について、貴重な情報までお寄せいただき、感謝しております。…
全体的にわかりやすく、特に「権利侵害投稿をリポストすることは権利侵害です」との部分は端的でわかりやすかったです。
まあそれはそうだろう…という感じですが、結局、元ポストが違法なものかどうかの判断がつくかには幅があるので、ユーザーとしては、違法ポストのリポストは基本的に違法というのを知っておいたうえで、これはアカンそうと感じられるものはリポストを控える、というのが必要なんでしょうね。まあ、それは常識的な結論のようにも思えます。
法的なリスク
リポストの違法性は、元ポストがどのような意味で違法であるか等によって分けると、イメージしやすいように思います。
リポストの法的なリスクとしては、
- 名誉毀損(民事責任・刑事責任ともに)
元ポストが名誉棄損に当たるような内容だった - 著作権・著作者人格権
元ポストが著作権・著作者人格権を侵害していた - 肖像権・パブリシティ権
元ポストが肖像権・パブリシティ権を侵害していた(ex. 肖像等を勝手に商品等の広告として使用) - 個人情報・プライバシー権
元ポストが個人情報保護法違反やプライバシー権を侵害する内容だった(ex. 顧客情報や内部資料) - 営業秘密漏えい/秘密保持契約(NDA)違反
元ポストが社外秘・営業秘密に該当する情報を含む投稿だった(ex. 社内資料の写真、未公表の価格・戦略等) - 信用毀損・業務妨害等(虚偽の風説・刑法233条)
元ポストが企業や個人の経済的信用を毀損するようなデマだった
といったものが考えられるかと思います。
リツイート事件最高裁判決というのも以前ありました。潮流自体は変わってない気がします(違法ポストのリポストは違法)。ただしここでリポストについて問題となっているのは、著作者人格権です。
以下のTMI解説などがわかりやすいです。
こういったリスクを踏まえた対応の心掛けとしては、
- 元ポストの出所(ex. 投稿者=著作者か、それとも転載か)を確認したか?(疑わしければ拡散しない)
- 投稿に他人の社会的評価や信用を低下させるような事実主張が含まれていないか? (含むなら拡散を控える)
- 個人情報や社外秘と思しき内容は含まれていないか? (含む場合は拡散禁止)
といったことを考えながら、一拍置く、ということだろうと思います。
プロフィール欄の注記は効果があるか
また、Xのプロフィール欄では、「リポストは必ずしも賛同を意味するものではありません」とか、リポストは備忘録/メモ代わりである旨の記載がなされていることがありますが、その意味についても考えてみたいと思います。
これは、法的な観点からいうと、名誉毀損や著作権侵害などで責任追及されたときに、「賛同の意思はなかった」と主張する材料になるのではと考える心理から来ているのだろうと思われますが、どうでしょうか。
結論からいうと、法的な効果は基本的にないと考えられます。
名誉毀損は他人の社会的評価を低下させることなので、「一般人がどう受け止めるか」という客観的評価が重視されます。裁判上も、リポストを賛同の意思表示と受け取れる事情があれば、プロフィール欄の免責的文言があっても責任が認められる可能性が高いと思われます。
注記自体に、民事責任に関する免責効果があるわけでもありません。相手方(被害者)の合意が存在するわけではないからです。
裁判所がプロフィール記載を「考慮要素」として少し斟酌する余地はゼロではありませんが、免責の決定打にはならないと理解するのが妥当と思われます。
法的責任はプロフィール欄ではなく、リポスト自体の内容・文脈・一般人の受け止め方で判断されます。
結び
以上、サクッと法務トピックでした。
個人的には、冒頭のポストのように、法務部名義で(つまり会社名義でなく)、対外部で広報的に法務が前面に出るのはけっこうな違和感がありますが、なぜか法務部の新しい動きとして注目されているようです。
まあ、いろいろ検討のうえでのことでしょうし、エンタメ業界という性質を考えると、権利侵害に対する厳しい姿勢を示す(そのようなイメージを持たせる)ような意味があるのだろうなとは思います。
[注記]
本記事は管理人の私見であり、管理人の所属するいかなる団体の意見でもありません。また、正確な内容になるよう努めておりますが、誤った情報や最新でない情報になることがあります。具体的な問題については、適宜お近くの弁護士等にご相談等をご検討ください。本記事の内容によって生じたいかなる損害等についても一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。